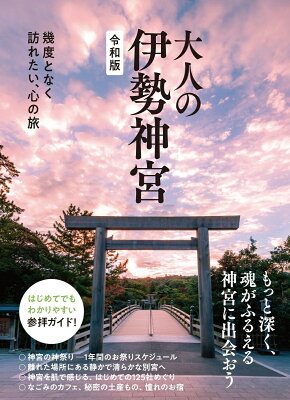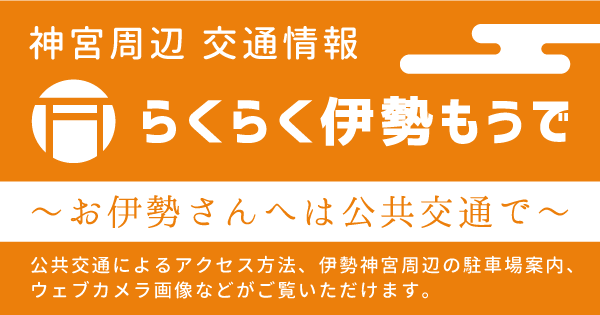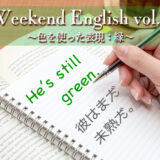スポンサーリンク

「お伊勢さんへおついたち参り日帰り弾丸ツアー」ご一行、
↓
↓
の参拝を終え、伊勢神宮内宮すぐそばにある「赤福」で小腹を満たし、
いよいよ満を持して?ついに伊勢神宮・内宮(皇大神宮)です!
目次 開く
- 伊勢神宮の正式名称は「神宮」
- 皇大神宮(伊勢神宮・内宮)の御祭神は天照大神
- 参拝は外宮→内宮、正宮→別宮
- 伊勢神宮内宮:参拝①「鳥居と宇治橋」
- 伊勢神宮内宮:参拝②「神苑と大正天皇御手植松」
- 伊勢神宮内宮:参拝③「手水舎と一の鳥居」
- 伊勢神宮内宮:参拝④「五十鈴川御手洗場」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑤超重要!「瀧祭神」へ
- 伊勢神宮内宮:参拝⑥正宮を目指します
- 伊勢神宮内宮:参拝⑦「正宮」
- 伊勢神宮内宮:ちょっと寄り道「大きな木」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑨「御稲御倉(みしねのみくら)」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑩「外弊殿(げへいでん)」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑪第一別宮「荒祭宮(あらまつりのみや)」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑫「風日祈宮(かざひのみのみや)」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑬「神楽殿」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑭「御厩(みうまや)」
- 参集殿で休憩
- 伊勢神宮内宮:参拝⑮「大山祇神社と子安神社」
- 伊勢神宮内宮:参拝⑯「宇治橋」へ
- 伊勢神宮内宮(皇大神宮)参拝のまとめ
- 痛恨のミス:「四至神」に行きそびれた
- 伊勢神宮・内宮(皇大神宮)

今さらではありますが、もう一度確認を。
「伊勢神宮」とよく聞きますが、実はこれ通称なんですよね。
正式には
「神宮」
のみ。
伊勢という地名はつかないんですね〜。
ちなみに「神宮」は、
- 内宮(ないくう)
- 外宮(げくう)
- 14所の別宮(べつぐう)
- 43所の摂社(せっしゃ)
- 24所の末社(まっしゃ)
- 42所の所管社(しょかんしゃ)
これらぜーんぶ125の宮社ひっくるめて「神宮」なのです。
規模がでかい。
そして、内宮・外宮も通称なんですね。
正式には、
- 内宮は「皇大神宮(こうたいじんぐう)」
- 外宮は「豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」
です。
テレビとかでよく聞く、いわゆる「伊勢神宮」は「皇大神宮(内宮)」のことを指してる時が多いですねぇ。
ちなみに、神宮の広さは神宮林などもあわせると、なんと約5,500ヘクタール!
東京ドーム約1,200個分!
めっちゃ広いね。なんせ伊勢市の面積の約1/6が神宮!ですからね。
すごい。

皇大神宮(内宮)の御祭神は、さんざん言っておりますが、
- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)
皇室の御祖先であり、日本人の総氏神であられます〜。
創建は、日本書紀によりますと、およそ2000年前の第11代垂仁天皇の御代の頃。
皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)が、天照大御神の御神体・八咫の鏡を鎮座する地を探し求めて、大和國から伊賀国〜近江國〜美濃國〜伊勢國を巡られたんですね。
なかなか大変ですね。
そして、伊勢国にたどり着いた時に、天照大御神が御自ら「ここがいい」とおっしゃったので、伊勢に鎮座することになりましたとさ。
で、天照大御神が気に入った五十鈴川のほとりに斎宮を建てたのが伊勢神宮、皇大神宮の始まりはじまりとなったのです。
それがおよそ2000年前。
まさに悠久の時。
伊勢神宮には「外宮先祭」という習わしがあるため、伊勢神宮にお参りするときは、
「外宮」から「内宮」
の順で参拝するのがよいとされてます。
そして、内宮・外宮とも、境内にはたくさんの宮社があるのですが、
まずは「正宮」。
それから「別宮」へ、という順で参拝していくのがいいそうです。
 【伊勢詣で】お伊勢参りへ行くなら参拝の順序は「外宮」から「内宮」だよ
【伊勢詣で】お伊勢参りへ行くなら参拝の順序は「外宮」から「内宮」だよ
 伊勢詣でに行くなら伊勢神宮参拝前に知っておきたい7つのこと
伊勢詣でに行くなら伊勢神宮参拝前に知っておきたい7つのこと

はい、ながながとウンチク垂れましたが、いよいよここから伊勢神宮内宮・皇大神宮へ!
五十鈴川に架けられた「宇治橋」を渡ると、そこから先は神域です。
今の宇治橋は平成21(2009)年11月3日に新しく架け替えられました。
全長はなんと101.8mもあるのです。

内宮は右側通行です。
ちゃんと「右側通行」の立て札も立ってるので迷わないですね。
まさに伊勢神宮の表玄関といったところでしょうか。
鳥居の前で一礼して進みましょう。
帽子をかぶってる人は帽子を外したほうがいいですよ。
実はこの鳥居、「冬至の日」の日の出に来ると……
鳥居の真正面から登っていく太陽が見えるのです!
果たして偶然か、それとも計算か……。
宇治橋の両端に建てられている鳥居、
内側の鳥居は内宮の旧正殿の棟持柱(むなもちばしら)、
外側の鳥居は外宮の旧正殿の棟持柱が使われてるのです。
しかも!
さらに20年が経つと、内側の鳥居は鈴鹿峠のふもとの「関の追分」、外側の鳥居は桑名の「七里の渡し」の鳥居になるのです。
つまり、
正殿の棟持柱を20年、宇治橋の鳥居になり更に20年、そして、関の追分・七里の渡しの鳥居になりさらに20年、
60年、お勤めを果たすのです。
すごい。まさにこれぞリサイクル。

天照大御神が気に入ったという五十鈴川。
宇治橋の上から。上流側ですね。
杭が建ってるけど、流木が宇治橋にあたるのを防ぐという橋を守る役目をしているのです。

宇治橋の内側、神宮側の鳥居を抜けると広々とした砂利道が広がります。

人の流れに乗って右側を歩きます。

この日は紅葉が綺麗でした〜。

砂利道を進むと右手に神苑が見えてきます。

大正天皇御手植えの松ってどれだろう?
これか?

こっち……?
わからない……。
どっちも違ってたりして……
神苑では春と秋の神楽祭公開舞楽も行われてます。

反対側には、神社などでよく見かけるお神酒?酒樽がありました。

神苑を過ぎ、さらに進むと小さな橋と鳥居が見えます。
はい!ここで一旦ストップです!
実はこの橋より向こうにはお手洗いはありませぬ!
伊勢神宮はかなり広いですからね、気になる方はここで用を済ませておきましょう。

橋を渡ると右手に、鳥居の手前に手水舎があります。
こちらでお清めをしておきましょう。
では一の鳥居をくぐって、五十鈴川の御手洗場へ。

鳥居をくぐり、進むと右手に「五十鈴川御手洗場(いすずがわみたらし)」が。
かつてはここでおき嫁をしていたんですね。

五十鈴川は「御裳濯川(みもすそがわ)」とも呼ばれてました。
八咫の鏡を持ち、諸国を探し歩いた倭姫命が、御裳のすそを濯いだ(服を洗ったってことかな)ことから名付けられたそう。
神路山を水源とする神路川と、島路山を源とする島路川の二つの流れが合流して五十鈴川となります。

石畳を進むと川辺まで行けます。
昔の人に倣って手を清めます。
まぁ川なので、手を清めるにとどめるのでいいかと。
心身を、心を、清めることが大事ですからね。
川底に硬貨が見えるのですが……硬貨を投げ入れちゃいけませんよ〜。
気持ちはわかるけどー。
自然の川ですからね。
立て看板にも硬貨の投げ入れはしないようにと書いてあります。
ちょっと豆知識。
五十鈴川御手洗場の石畳ですが、
あの!犬将軍で有名な第5代将軍徳川綱吉の御生母・桂昌院(けいしょういん)様が御寄進されたんだとか。
結構、見落とされがちなんですが、この「瀧祭神」超重要!なんです!
とか言いながら写真撮り忘れました。てへ。
五十鈴川で手を清めたらそのまま参道に戻っちゃいそうなくらい、ひっそりとしてるんですが、右手に細い山道があります。
そこを見逃さず「瀧祭神」へ向かいましょう。
「瀧祭神」は内宮の所管社の一つ。
ん?いやいやまず正宮にお参りしてからでしょ、と思いますよね。
実はこの「瀧祭神」、古くから「とりつぎさん」とも呼ばれているのです。
御垣と御門のみで社殿がないので、ん?お社かな?と戸惑うのですが、こちらには瀧祭大神(たきまつりのおおかみ)が祀られています。
五十鈴川の守り神なのです。
しかも、この瀧祭大神は天照大御神に、
「これこれこういう者が参拝に来られましたよ」
と取り次いでくれるのです!
「とりつぎさん」とは「取り次ぐ」なんですね〜。
だからここだけは正宮より先に参拝するのですよ。
まぁ現代風にいうなら「受付」?みたいな。
「どこそこから来ました。ほにゃららです。天照大御神にご参拝に来ました」
みたいな感じですね。
ちなみに伊勢では、毎年8月1日の八朔の日に、五十鈴川で汲んだ水を瀧祭神にお供えして、家に持ち帰り、神棚で無病息災を祈る風習があるそうです。

瀧祭神で受付を済ませたら、再び参道へ。
緑生い茂る道を歩いてると、ほんとにここだけ時間の流れが違いますねぇ。
心が洗われるような気持ちになります。(笑)
二の鳥居の先には、右手に風日祈宮へ行く参道と、左手には神楽殿がありますが、お守り・御朱印は一旦ガマンして正宮へと向かいましょう。

そして、ついに来ました!
伊勢詣での最大のハイライト!
伊勢神宮内宮(皇大神宮)の御正宮です!

石段を20段ほど登った先に、天照大御神が座す御正宮が!
撮影ができるのは石段の下からのみ!ですよ!
天照大御神は、皇室の祖先、そして日本人の総氏神。
えーしつこく何度も書いておりますが、個人的なお願い事をする場所ではないのです!
お賽銭箱もありませんからね。
投げ入れるなんてそんな罰当たりなことしちゃいけないよ。
日々の感謝をお伝えしましょう。
あ、「二礼二拍手一礼」です。
御正宮の鰹木は10本(偶数)で、千木は内削ぎの水平です。
お社の屋根の形で祀られている神様の系統がわかるというのを外宮の参拝記事にも書きましたが、天照大御神は女神なので、鰹木は偶数で千木は水平になるのですね。
参拝を終えたら、石段を戻るのではなく、左手に進むと帰り道があるのでそちらを通りましょう。
 【伊勢詣で】ついに到着!伊勢神宮内宮(皇大神宮)!二千年の悠久の時を感じられるまさに日本人の心のふるさと
【伊勢詣で】ついに到着!伊勢神宮内宮(皇大神宮)!二千年の悠久の時を感じられるまさに日本人の心のふるさと

参道の途中、めっちゃ大きな木がありました。
なんかみんな木に触っていたので、パワースポット?的な?
明らかに手が触れたところはツルツルしてました。

木のくぼんだところが、気持ちいいくらいスッポリはまりました。
大きな揺りかごにでも抱っこされてるような感じです。
(写真の人物は「お伊勢さんへおついたち参り日帰り弾丸ツアー」の仲間・笑)

御正宮の参拝を終え、第一別宮の荒祭宮へ向かう途中にある「御稲御倉(みしねのみくら)」。
神宮神田で収穫した御稲が奉納されてます。
稲を保存するため高床式の造りになってますね。
教科書に出てくる高床式がこんな間近で見れるとは。
小さいですが、正宮と同じ神明造でれっきとしたお社です。

こちらも神明造の高床式の建物。

はい、きました。
伊勢神宮内宮の第一別宮・荒祭宮。
御祭神は天照大御神の荒御魂。
個人的なお願い事などをしたい時は、こちらでお参りしましょう。

こちらは千木は水平ですが、鰹木は6本(偶数)ですね。

石段を突き破るようにそびえ立つ木。

表参道に戻ると左手に神楽殿が見えてきますが、右側に風日祈宮へ行く参道があります。

風日祈宮は橋を渡った先にあります。

風日祈宮。
千木が水平ですね。

鰹木は6本(偶数)かな。
風日祈宮の御祭神は級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)。
外宮の別宮・風宮と同じ御祭神です。
伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の御子神で風雨を司る神様です。
風雨は農作物に大きな影響を与えるので農作物の神様でもあります。
そして、この神様といえば!
鎌倉時代の2度の元寇の際、蒙古襲来の時に神風を吹かせて日本を守った神様です。
毎年5月14日と8月4日には、風雨による災害が起こらないように風日祈祭が開催されています。

表参道のほぼ中間地点にあるのが神楽殿。
ご祈祷のお神楽などが行われます。

神楽殿の横にあるのがお神札授与所。
御朱印や御神札や御守などはこちらで。

でかい。はいりきらない。
向かって左側からお神札授与所、ご祈祷受付、御饌殿、神楽殿。
神様の乗り物とされる神馬がいる場所なんだけど。
もうお馬さんいなかった。
神馬は、毎月1日、11日、21日に正宮にお参りするそうです。
外宮で見れたから良しとするか。
御厩の近くには、「参集殿」という休憩所があります。
神楽殿の建物に沿って右に折れるとその先に御厩と参集殿があります。
お茶も飲めるので、ちょっとここらで一息入れましょう。
参集殿には能舞台もあり、ここで奉納行事も行われるそうです。
ここでもお守りや、伊勢神宮関連の本などが売ってました。

参集殿をすぎ、さらに奥へと進むと子安神社と大山祇神社があります。
鳥居の向こう、横、にあるのですが、え?神社?という印象。
瀧祭神と同じような感じで、御垣と御門のみの造りです。

子安神社の御祭神は、木華咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)。
安産や子授け、縁結びの神様です。
そして子安神社の奥にあるのが大山祇神社(おおやまつみじんじゃ)。
御祭神は、神路山の入口の守護神である大山祇神。
隣に座す、木華咲耶姫命の父神です。

子安神社と大山祇神社の参拝を終え、これで伊勢神宮・内宮の参拝は完了!
宇治橋へと戻ります。

戻ってきましたねぇ。
宇治橋を再び渡り、俗世へと還っていくんですねぇ。

帰りの宇治橋から見た五十鈴川。下流の方ですね。

五十鈴川を見ると、鳥がいました。
ちょっと遠くてピントがイマイチ。
ピントというか自分の腕……?

最後に忘れてならないのが宇治橋の擬宝珠(ぎぼし)!
実はですね、
は〜全部参拝終えたよしよし
と満足してのほほんと宇治橋を渡りきってはいけません。
宇治橋の、ある擬宝珠の中に、橋の安全を祈った御札が収められているのです。
そして、この擬宝珠に触れて帰ると、また参拝に訪れる事ができると言われているのです。
それは、宇治橋の西側、おかげ横丁側から、つまり下流側、そして入り口から2本目の擬宝珠です。
内宮は右側通行となってますので、触るとしたら帰りになりますね。
つまり最後から2本目、鳥居の手前の擬宝珠です。
まぁたくさんの人が触ってるし、文字も刻まれてるのですぐわかると思います。
一応、自分はこんな風にまわったよ、とまとめてみました。
が!まぁぶっちゃけてしまえば、伊勢神宮の参拝の際に、絶対にこうしなきゃいけない!
ってものはないです。
ただまぁ二千年という長〜い歴史の中で、こうしたほうがいいだろうと、だんだんとカタチになり、作法が出来上がり、いわゆる伝統的な正式な参拝方法とか、しきたりなるものができていったのではないかと。
カタチにこだわりすぎる必要はないけれど、作法というのは掘り下げていくとひとつ一つ意味が込められていたりするものですからね。
「お詣り」をするときには敬虔な気持ちや感謝の気持ちを持って、お参りするのが一番だと思います。
もしこれから伊勢神宮行くよ〜という方のご参考にでもなれば。
伊勢神宮の境内の四方を守る、「四至神(みやのめぐりのかみ)」。
社殿や御垣はなくて、石畳の上に祀られているだけなんですが……
どうやら、伊勢神宮の最強パワースポット!らしい。
神楽殿の近くにあります。
まさに痛恨のミス!
あ、お社はないけど神様が祀られてるとこですから、手をかざすんじゃなくてお参りするなら二拝、二拍手、一拝」ですよ。
| 所在地 | 三重県伊勢市宇治館町1 |
|---|---|
| 参拝時間 | 1月~4月 5:00~18:00 5月~8月 5:00~19:00 9月 5:00~18:00 10月~12月 5:00~17:00 |
| 休日 | なし(年中無休) |
| 駐車場 | 1800台くらい |
| アクセス |
|
| URL | http://www.isejingu.or.jp |
駐車場はかなり広いです!
しかしそれ以上に参拝者が多いです!
なので駐車場情報はこまめにチェックしましょう。